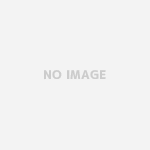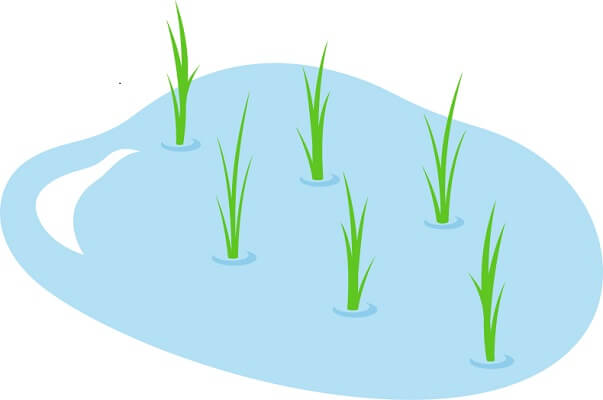
6月になると「夏至」があります。夏至と聞くと夏?と思う方もいるかもしれませんが、そもそも夏至とはどういったものなのでしょうか?
また、夏至の時に食べる風習も地域によって違ってきます。どういったものが食べられているのでしょうか?
夏至とはどういう意味?
毎年6月21日頃は「夏至(げし)」になります。
夏至は北半球では、一番昼の時間が長い日です。
その年によって日にちがずれることもあるため、6月21日頃となります。
夏至は立春などと同じ、二十四節気のうちの1つで10番目になります。
芒種(ぼうしゅ)6月5日頃
→夏至(げし)6月21日頃
→小暑(しょうしょ)7月7日頃
と続きます。
また、夏至は、6月21日頃から、次の小暑(7月7日頃)の前日までの期間を表すこともあります。
日本では梅雨の時期なので、あまり夏のイメージはないかもしれませんね。
一番日の出が早い日とか、一番日の入りが遅い日とかと思われている方もいらっしゃいますが、夏至とは一致していません。それぞれ一週間くらいずれがあります。
また、一番昼間の短い冬至との昼間の差は場所にもよりますが、5時間から6時間の差があります。
農家では田植えのシーズンにあたるため、とても忙しい時期です。
雑節の一つに半夏生(はんげしょう)というのがあります。
この半夏生(はんげしょう)は、夏至から11日目にあたる日ですが、このころまでに田植えを終わらせるという目安にされていました。
雑節というのは、中国から来た二十四節気は日本の気候と少しズレがあるので、日本の気候にあわせてでつくられた特別な暦日のことです。
雑節の仲間には、節分、彼岸、八十八夜、土用などもあります。
夏至は、二至(夏至、冬至)二分(春分、秋分)というように、
二十四節気のなかでは、重要なものの一つです。
夏至の食べ物の風習は?
冬至にはかぼちゃを食べる風習がありますが、夏至にもあります。
夏至の場合、各地でそれぞれの習慣があるようです。
関西では、夏至にタコを食べます。
タコの足のように稲がしっかり根付くように
という願いが込められているようです。
京都では水無月という和菓子を食べます。
水無月はういろうの上に小豆が乗っていて、
上から見ると三角形の形に切り分けられたお菓子です。
関東では小麦餅を作り神様にお供えします。
奈良でも小麦餅を作ります。これを「半夏生餅」といいいます。
島根や熊本でも小麦の団子やまんじゅうを神様にお供えします。
福井ではサバを食べます。
香川ではうどんを食べます。
愛知ではいちじくに味噌をつけた田楽を食べます。
夏至の七十二候は?
七十二候は、二十四節気のそれぞれを約5日ずつ「初候」「次候」「末候」の3つに分けた期間で、それぞれの期間がどんな季節なのかを表します。
初候:乃東枯(ないとう かるる)
夏枯草が枯れる時期です。
乃東(ないとう)というのは夏枯草(なつかれくさ)のこと
漢方薬に使われます。
次候:菖蒲華(しょうぶ はなさく)
あやめの花が咲く時期です。
菖蒲は「あやめ」のこと。
末候:半夏生(はんげ しょうず)
烏柄杓が生える
半夏は烏柄杓(からすびしゃく)のこと。
烏柄杓という薬草が成長する時期です。
まとめ
夏至は毎年6月21日頃になります。
二十四節気のひとつで10番目になります。
北半球では、昼の時間が一番長い日です。
また、このじきは梅雨の時期であり、農家では田植えをこのシーズンに行う大事な時期です。
夏至にはタコを食べたり、小麦餅を食べたりと、各地でいろいろな風習があります。
夏至の時期は夏というより梅雨のイメージが強いので、昼が長いといってもピンとこないこともありますよね。
農業に携わる人たちにとっては、大事な時期なんですね。