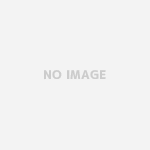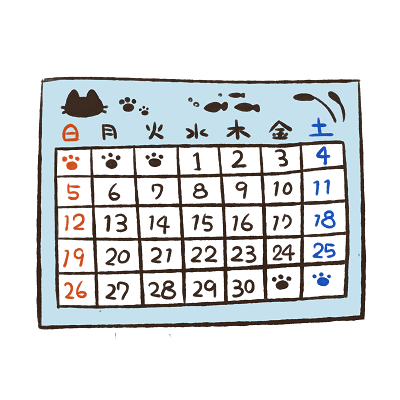
二十四節気っていう名前自体は、あまり馴染みはないかもしれませんが、「立春」とか「夏至」も二十四節気って言われると何となく想像できる人も多いのではないでしょうか。
立春や夏至も二十四節気なのですが、他に22個もあります。その中には「寒露」などのように、読み方もわからず、あまり聞き覚えのないものもあります。
二十四節気とはそもそもどういうものなのでしょうか。
二十四節気とはどういう意味?
二十四節気はもともとは古代中国でできたもので、12の節気と12の中気が交互におかれています。
太陰暦は、月の動きを元にしていたため、太陽の動きと関係のある季節が年ごとに、少しずつ暦とずれてきてしまっていました。
農耕などでは、季節がずれてしまっては不便になってしまうので、暦から季節がずれてしまっても、季節を知り、調整するために設けられていました。
もともと中国の気候から名前が付けらてていたので、日本と合わない名前もあります。
そのため、日本では、土用、八十八夜、二百十日などの「雑節」というものを別に設定しています。
二十四節気は、「黄道」と言われる地球から見た太陽が移動する楕円形の線を元にしています。
春分の地点が起点となってスタートして1年で1周します。
1週360度を24個で分けると、1個につき15度ずつとなります。
この24個に分割した地点が二十四節気となります。
現在でもよく名前を聞くこともある「夏至」や「冬至」は二至(にし)、また、「春分」「秋分」は二分(にぶん)といいます。
また、「立春」、「立夏」、「立秋」、「立冬」を四立(しりゅう)といいます。
さらにこれら8つを八節(はっせつ)といいます。
八節それぞれの期間を3つに分けたものが二十四節気となります。
ちなみにこの二十四節気をさらに3つに分けたものが「七十二候」と呼ばれるものになります。
二十四節気は、毎年同じ日とは決まっていません。そのとしによって、若干前後します。
二十四節気の読み方の一覧
二十四節気の中には立春や夏至、秋分など現在でもつかわれていて普段よく耳にするものもありますが、芒種、寒露など馴染みのないものもありますね。
また、年によって日付が変わってしまうことから〇月〇日「頃」としてあります。
正確に知りたい場合はカレンダーなどで確認してください。
二十四節気は立春が起点となり、節気「節」と中気「中」が12個ずつ交互になっています。
※ふりがなの後に記載されています。
【春】
立春(りっしゅん)節 2月4日頃
雨水(うすい)中 2月18日頃
啓蟄(けいちつ)節 3月5日頃
春分(しゅんぶん)中 3月20日頃
清明(せいめい)節 4月4日頃
穀雨(こくう)中 4月20日頃
【夏】
立夏(りっか)節 5月5日頃
小満(しょうまん)中 5月21日頃
芒種(ぼうしゅ)節 6月5日頃
夏至(げし)中 6月21日頃
小暑(しょうしょ)節 7月7日頃
大暑(たいしょ)中 7月22日頃
【秋】
立秋(りっしゅう)節 8月7日頃
処暑(しょしょ)中 8月23日頃
白露(はくろ)節 9月7日頃
秋分(しゅうぶん)中 9月23日頃
寒露(かんろ)節 10月8日頃
霜降(そうこう)中 10月23日頃
【冬】
立冬(りっとう)節 11月7日頃
小雪(しょうせつ)中 11月22日頃
大雪(たいせつ)節 12月7日頃
冬至(とうじ)中 12月21日頃
小寒(しょうかん)節 1月5日頃
大寒(だいかん)中 1月20日頃
例えば立春というと、2月4日の事を言うこともありますが、2月4日から立春の次の二十四節気の雨水の前日までの期間のことを言う場合もあります。
まとめ
二十四節気とは、中国から来たもので、月の動きを基準とする暦と、太陽の動きが基準となる季節が、年ごとにずれてしまうことから、季節を知ることができるように使われてきました。
太陽の動く楕円の軌道を24に分け、それぞれに名前が付けられました。そのうち「立春」や「夏至」など、現在でも使わているものも多くあります。