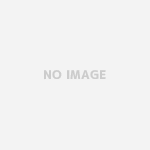5月のカレンダーによく小さい文字で書かれている「小満」。
あまり馴染みのない言葉だと思う人も多いのではないでしょうか?
この小満とは、いったいどういう意味があるのでしょうか?
小満芒種という言葉がありますが、これはどういう意味なのでしょうか?
また、この時期の季節を表す七十二候についても見てみましょう。
小満とはどういう意味?
毎年5月21日頃が「小満」にあたります。読み方は「しょうまん」と読みます。21日と固定されているわけではなく、年によって前後します。
小満とは二十四節気と呼ばれるものの一つです。二十四節気とは一年を24の期間に分けて、季節にかかわる名称がつけられているもので、立春や夏至なども二十四節気の仲間です。
立春や夏至に比べると、「小満」はあまり知られていない印象ですね。
小満は二十四節気のうちの8番目にあたります。
※1番目は立春になります。
立夏(りっか)5月5日頃
→ 小満(しょうまん)5月21日頃
→ 芒種(ぼうしゅ)6月5日頃
と順に移っていきます。
また、小満は5月の21日頃から次の芒種(6月5日頃)の前日までの期間を表すこともあります。
気候が良くなり、草木も次第に成長して生い茂る時期です。
初夏で、秋に蒔いた麦などに穂がつくころです。そこで順調に穂がつくことで一安心という意味もあるようです。
この時期、麦が熟するころ降る雨のことを麦雨(ばくう)、風のことを麦嵐(むぎあらし)とよびます。
小満芒種ってなに?
小満芒種という言葉がありますが、これはどういう意味なのでしょうか?
芒種とは「ぼうしゅ」と読み、小満と同じく二十四節気の一つで6月5日頃にあたり、小満の次に来るものです。
小満芒種というのは、沖縄県では梅雨の事を表しています。
沖縄県では、5月から6月にかけてが梅雨の時期となります。
その時期が二十四節気で言う「小満」「芒種」にあたることから沖縄では梅雨のことを「小満芒種」と呼びます。
「スーマンボースー」と読むようです。
小満の七十二候は?
二十四節気の一つの期間はそれぞれが約15日です。
七十二候は、その二十四節気それぞれを約5日ずつ「初候」「次候」「末候」の3つに分けた期間で、それぞれの期間がどんな季節なのかを表します。
初候:蚕起食桑(かいこ おこって くわを くらう)
蚕(かいこ)が桑の葉を盛んに食べ始める
次候:紅花栄(こうか さかう)
あたり一面、紅花が盛んに咲く
末候:麦秋至(ばくしゅう いたる)
麦の穂が実り麦秋となる
麦秋というのは、麦の穂が実り、麦の刈り入れの時期を迎えた初夏のころのことで、収穫期のことを秋といい、麦の収穫期という意味です。
まとめ
「小満」は毎年5月21日頃にあたります。二十四節気の8番目になります。
この時期は初夏にあたり、草木も次第に成長している頃です。
沖縄県では「小満芒種」という言葉があり、「芒種」とは、二十四節気の小満の次に来るものです。
沖縄では、「小満」「芒種」のころ、5月から6月にかけて梅雨となるため、「小満芒種」は梅雨の事を意味し、「スーマンボースー」と読みます。
小満は同じ24節気の立春や夏至などに比べると、なかなか知られていませんが、麦の収穫の時期にあたるため、大切な時期だったんですね。